『信念に生きる―ネルソン・マンデラの行動哲学』リチャード・ステンゲル |集団で生きるすべをマンデラから学ぶ
- 2025年9月9日
- 読了時間: 6分
【書評・レビュー】
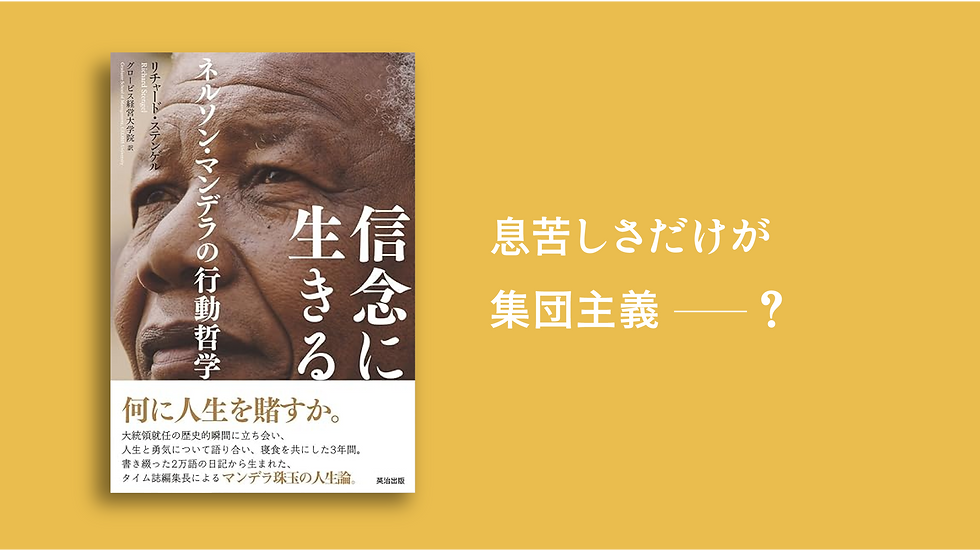
息苦しさだけが集団主義?
「集団主義」と聞くと、同調圧力や息苦しさを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。空気を読んで黙ること、個人の意見を抑えること──そんなイメージが、日本では根強く残っています。
けれど「集団主義」には、互いを支え合う「共生型」と、従わせてまとまろうとする「統制型」があります。
戦時を契機に日本では後者が刷り込まれ、その影響が今の社会にも影を落としています。
一方、アフリカの思想 ウブントゥ が示すのは「共生型の集団主義」。
個を消すのではなく、互いの存在を通じて個を活かし合う考え方です。
この本は、赦しと和解を選び抜いたネルソン・マンデラの行動哲学から、
「集団での生き方」を改めて問い直す一冊です。
ネルソン・マンデラの歩みと功績
ネルソン・マンデラ(1918–2013)は、南アフリカの人種隔離政策「アパルトヘイト」と闘い続けた人物です。
若くして弁護士として活動し、アフリカ民族会議(ANC)のリーダーとして反政府運動に参加。
国家反逆罪で逮捕され、27年もの長い獄中生活を送りました。
それでも「黒人と白人の融和」を訴え続け、釈放後は対立ではなく「和解」を選び取りました。
1994年、南アフリカ初の全人種参加の選挙で大統領に就任。
赦しと和解を土台に「虹の国」と呼ばれる多民族国家の再建を主導しました。
その姿勢は世界中から称賛され、1993年にはノーベル平和賞を受賞。
生涯を通して「自由・平等・和解」の象徴として尊敬され続けています。
『信念に生きるーネルソン・マンデラの行動哲学』の魅力と内容
本書の中心にあるのは「リーダー論」です。ネルソン・マンデラがどのように人を率い、困難な局面で決断してきたのか──その具体的な姿勢が描かれています。
著者リチャード・ステンゲルが2年間にわたり密着取材したことで、単なる理想や美談ではなく、リアルなエピソードとして語られるのが大きな魅力です。牢獄での過酷な経験、大統領就任後の人種間の緊張、敵と向き合う場面など、ひとつひとつが「生きた哲学」として迫ってきます。
その中でも私が特に学びを得たのは、マンデラの「人との接し方」です。
誰であっても必ず相手の良い面を見つけようとする姿勢、相手を尊重しながら信頼を築いていく態度は、根底に ウブントゥ の思想──「人は他者を通じて人となる」──があるからこそだと感じました。
その姿勢をよく表しているのが、獄中での看守との関わり方です。
マンデラの同志たちは、刑務所の看守たちのことを、アパルトヘイトという冷徹なシステムを具現化する実行者グループとみなしていた。一方で、マンデラは彼らの中にも、親切さや尊敬に値する面があるのではないかと考えていた。ほとんどの看守たちは、十分な教育を受けておらず、子供の頃から不公平なシステムの中で育ち、人種差別という思想を叩き込まれてきた。貧しい育ちのものが多く、境遇は大部分の受刑者たちと大差ないものだった。
敵対関係を前提とせず、相手を「同じ人間」として見つめる姿勢。ここにウブントゥの思想がにじみ出ています。
集団主義の中で必要以上に傷つかないための視点
私がこの本で最も感銘を受けたのは、次の一説です。
その編集者は自分の利益のために行動しただけで、マンデラを欺こうとしたわけではない。だから、これは取るに足らないことだと考えて実際あまり相手にしなかった。
人は誰かの行いに傷ついたとき、「故意に傷つけられた」「自分を大事に思ってくれなかった」と感じ、悲しんだり恨んだりしてしまいます。けれど実際には、相手は私を攻撃したのではなく、自分を守るための行動をしただけ──そういうことが多いのだと気づかされました。
この考え方に触れてから、私は必要以上に悩んだり傷ついたりすることが減りました。むしろ、人に配慮する余裕すらなくなった相手の境遇を思いやれるようになりました。
集団で生きることとは、「無理やりみんなと同じ考えを持ち仲良くすること」ではありません。集団の中にはそれぞれ独自の考えや行動原理を持つ人々がいて、ただ同じ国や組織に所属し、共通の目標を共有しているだけです。
それでも共生型の集団主義が人々を幸せにできるのは、違いを尊重し合える人々の中で自分の存在意義を感じることができるからです。
そのような健全な集団を導く秘訣を、マンデラは子どもの頃から学んでいました。
子どもの頃から、私は集団的リーダーシップには二つの意義があると学んでいた。一つは、個人の知恵よりも集団の知恵が勝るということ。そしてもう一つは、全員の合意形成のプロセスを経た結論には尊さがあるということ。(…)全員の調和を保ちながらゴールに達することができる。それはみんなにとって望ましいことであり、同時にリーダー自身にとっても望ましいことなのだ。
個々の存在意義を認め合いながら、集団でしか得られない幸せを分かち合う──それこそがまさにウブントゥの思想に通じる「共生型の集団主義」の魅力であり、私たち日本人が忘れてしまった感覚だと改めて感じました。
日本はこれからも集団主義の文化を色濃く持ち続けるでしょう。そうであれば、より良い集団主義のかたちを選び取り、その中で幸せに生きる方法を探っても良いのではないでしょうか。
私が構想しているミュージカル『最果てのミューズ』は、明治・現代・未来をまたぐ作品です。舞台は日本──だからこそ、未来の社会で「どんな集団主義を生きるべきか」を問い続けたいと考えています。
まとめとおすすめ|『信念に生きるーネルソン・マンデラの行動哲学』はこんな人に読んでほしい
『信念に生きる ネルソン・マンデラの行動哲学』は、マンデラの言葉や姿勢を「理想論」ではなく、現実のエピソードとともに伝えてくれる一冊です。
「人を赦す」「敵をも尊重する」と聞けば遠い理想のように思えますが、本書ではそれがいかに実践され、現実を動かしてきたかが描かれています。そこにこそ学びがあります。
リーダーとして悩んでいる人はもちろん、組織の中で息苦しさを感じている人にも、自分の立ち位置を見直すヒントになります。
マンデラの哲学は、リーダーのためだけでなく、私たち一人ひとりにとって「どう集団と向き合うか」を考えるための道しるべになるはずです。
こんな方におすすめです
• リーダーシップに悩んでいる人
• 職場や組織の人間関係で息苦しさを感じている人
• ウブントゥの思想や「共生型の集団主義」に関心がある人
• 歴史に学びながら、自分の価値観をアップデートしたい人


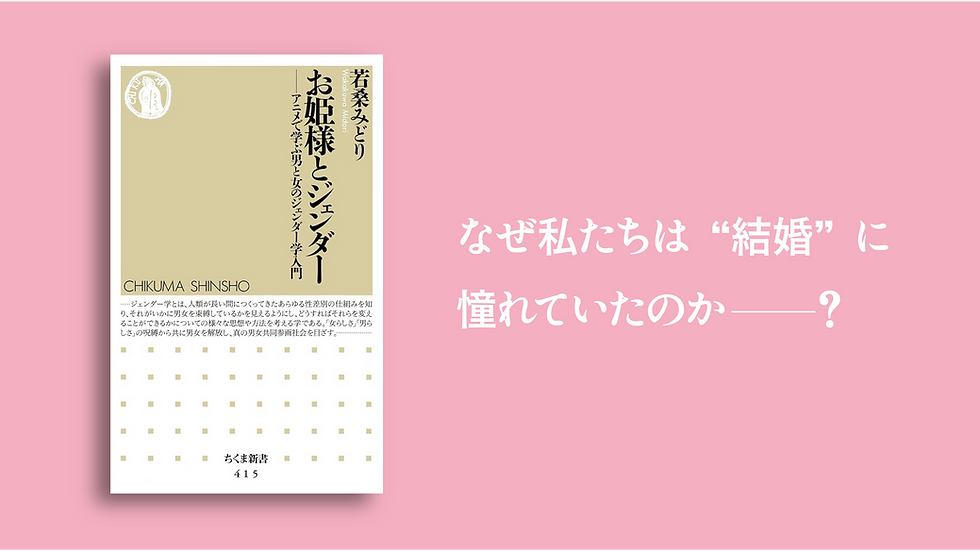
コメント